投稿日2025.4.4
食品添加物の着色料は安全?危険性や使われている食品を解説
スーパーやコンビニで食品を選ぶとき、食品表示を見て「赤〇号」「青〇号」などの表記に不安を感じたことはありませんか?
これらはすべて食品添加物の着色料であり、食品の見た目を良くするために使われています。
本記事では、食品添加物の着色料について、安全性・種類・よく使われる食品・避け方まで、徹底解説!
目次
食品添加物の着色料とは
食品添加物の着色料は食品の色調を改善するために使用されます。
しかし、種類、安全性について詳しく知っている人は意外と少ない状況です。
ここでは、食品添加物の着色料について以下のような項目を踏まえて詳しく解説していきます。
- 合成着色料と天然着色料の違いとは
- 着色料の使用用途
合成着色料と天然着色料の違いとは

2024年に食品添加物の不使用表示に関する新たなガイドラインが施行されました。
「合成」「天然」等の表現は禁止され、具体的な成分名を明記することが必須に。
本記事ではわかりやすくするため、「合成」「天然」表記を使用しています。
食品着色料には大きく分けると「化学合成系着色料」と「天然系着色料」に分類。
化学合成系着色料は、化学的に合成された人工の色素で、天然系着色料は、植物や昆虫などの自然由来の成分を抽出した色素です。
以下でそれぞれの特徴を表にしましたので参考にしてください。
| 種類 | 特徴 | 例 |
| 化学合成系着色料 |
| タール色素(赤色〇〇号、青色〇〇号) 水溶アナトーなど |
| 天然系着色料 |
| ウコン色素 クチナシ青色素 コチニール色素 トマト色素 ニンジンカロテンなど |
「天然=安全」「合成=危険」と単純に決めるのではなく、それぞれの成分の特性や安全性を理解して選んでいくのが重要です。
アイチョイスではカラメル色素Ⅰやクチナシ黄色素など、天然系の着色料のみに使用を限定しています◎
着色料の使用用途

着色料には以下のような重要な役割があります。
- 食品の見た目を良くする
- 食品の品質を安定させる
- 本来の色を補う
- ブランドイメージを維持する
以下で内容について詳しく解説します。
食品の色調を改善する
人間は「視覚」から食欲を刺激されます。
たとえば、カレーの黄色(ウコン色素)や、イチゴジャムの赤(コチニール色素)が自然な色合いでなければ、食欲が湧かないかもしれません。
とくにお菓子などの加工食品などは美味しそうな見た目は重要。
食品添加物の着色料は、「美味しそうに見せる」ための役割を果たしています。
本来の色を補う
果汁飲料やスイーツなどは、加工の過程で元の食材の色が薄くなってしまいます。
たとえば、ストロベリーアイスクリームは、本物のイチゴだけでは淡いピンク色にしかなりません。
より鮮やかで美味しそうに見せるために、着色料が使われるのです。
ブランドイメージを維持する
食品メーカーは「いつ買っても同じ色・同じ味」の商品を提供することが求められます。
そのため、食品の見た目の均一性を保つために着色料が活用されるのです。
食品添加物の着色料は本当に危険?

着色料はすべてが危険というわけではありません。
食品添加物の着色料は、国の厳しい基準をクリアしたもののみ使用が許可。
日本では「食品衛生法」に基づき、厚生労働省が安全性を審査した上で、使用を認めたものだけが食品に添加されています。
国際的には「ADI(1日摂取許容量)」という基準が設定されており、「生涯にわたって毎日摂取しても健康に影響がないとされる量」も定められているのです。
ADIの範囲内であれば、基本的には健康への悪影響はないとされています。
しかし、一部の合成着色料には健康への悪影響が懸念されているものも。
たとえば以下のような着色料です。
| 着色料 | 指摘内容 |
| 食用タール色素 (赤色102号・赤色40号・黄色5号など) |
|
| コチニール色素(E120) |
|
食品表示をよく確認し、自分や家族にとっての最適な選択をしましょう。
参考:食用赤色3号のQ&A|消費者庁,(参照2025-02-27)
参考:コチニール色素に関する注意喚起|消費者庁,(参照2025-02-27)
食品添加物の着色料にはどんな種類がある?
食品に使われる着色料を一覧に考えると、以下のようになります。
| 着色料 | 主な使用食品 | 特徴 |
| アナトー色素 | チーズ、マーガリン、ハム、ソーセージ | ベニノキ科ベニノキの種子か ら得られる色素 |
| ウコン色素 | カレー粉、漬物 | ショウガ科ウコンの根茎から抽出して得られる色素 |
| カラメル色素 | 炭酸飲料(コーラ)、ソース、醤油 | ブドウ糖などの糖類を加熱処理して得られる色素 |
| カロチン色素(カロチノイド色素) | バター、マーガリン、お菓子類 | にんじんやトマトから抽出される色素で主成分がカロテン |
| クチナシ色素 | 和菓子、麺類、漬物 | アカネ科クチナシの果実から得られる色素 |
| コチニール色素 | 清涼飲料水、酒精飲料、菓 子、かまぼこ | カイガラムシ科のエンジムシという昆虫の乾燥体から得られる色素 |
| 食用タール系色素 | 漬物、かまぼこ、菓子 | 12種類が指定され、使用できない食品がある |
| 銅クロロフィル・銅クロロフィリンナトリウム | 青汁、ミント系食品 | 植物体内にあるクロロフィルの分子中のマグネシウムを 銅に置き換えて作られた色 素 |
| ベニコウジ色素 | 練り製品、調味料 | カビの一種であるベニコウジ菌の培養物から得られる色素 |
| ベニバナ赤色素・黄色素 | 清涼飲料水、菓子、麺類 | キク科ベニバナの花から得られる色素 |
アナトー色素
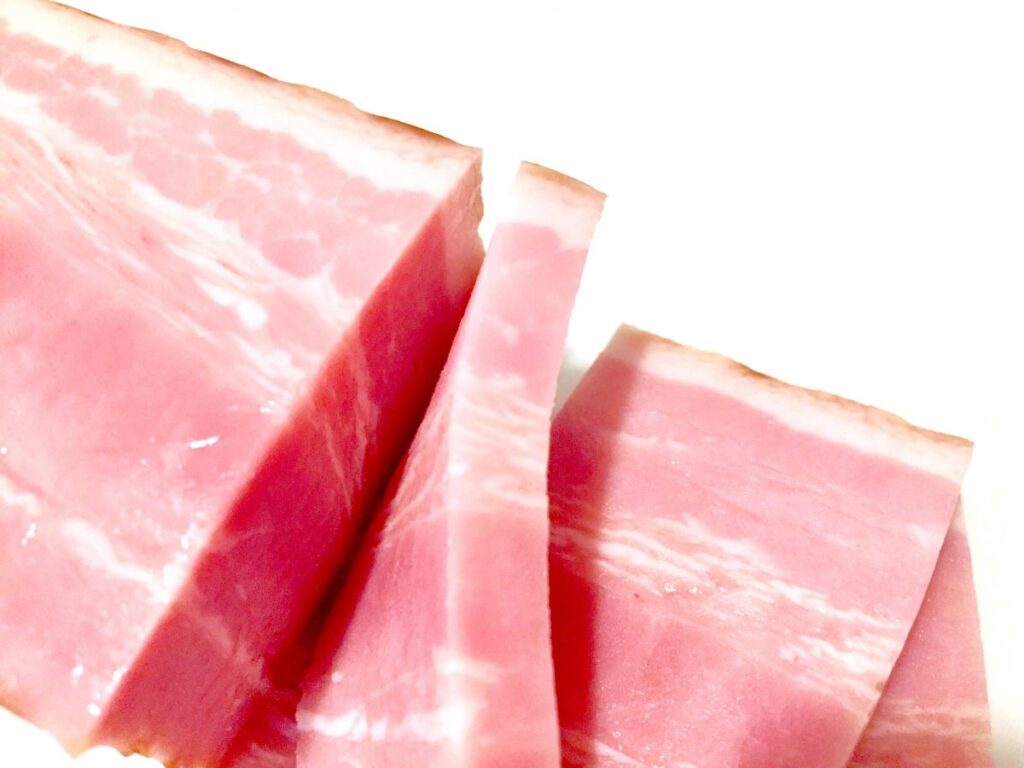
天然系着色料で、ベニノキ(アナトー)の種子から抽出される黄色系の色素です。
- 由来:ベニノキの種子
- 主な用途:ハム、ソーセージ、チーズ、マーガリン
- 性状:黄色〜橙色
ウコン色素

ウコン(ターメリック)の根茎から抽出した色素で「クルクミン」という成分が含まれ、抗酸化作用や肝機能の改善効果が期待できます。
- 由来:ウコン(ターメリック)
- 主な用途:カレー粉、からし、漬物
- 性状: 黄~暗赤褐色
カラメル色素

カラメル色素には4つの種類があり、糖類を加熱処理して作られる褐色の色素です。
- 由来:糖類やデンプンの加水分解物、糖蜜などを加熱処理
- 主な用途:コーラ、ソース、醤油
- 性状:暗褐~黒色
カロチン色素・カロチノイド色素

β-カロチン(ビタミンAの前駆体)を含む色素で、抗酸化作用があり、目や皮膚の健康維持に良いとされています。
- 由来:にんじんやトマトなどの植物
- 主な用途:バター、マーガリン、麺類、菓子
- 性状:赤紫~暗赤色
クチナシ色素

クチナシの果実から抽出される色素。
- 由来:クチナシの果実
- 主な用途:菓子、アイスクリーム、漬物
- 性状:暗赤紫~赤色(青)、暗赤紫~赤色(赤)、黄~暗赤色(黄)
コチニール色素

昆虫由来の着色料で、イチゴミルク、ハム、カニカマなどの赤色を出すのに使用されています。
- 由来:昆虫(カイガラムシ)
- 主な用途: アイス、飲料、化粧品
- 性状: 赤~暗褐色(アレルギーの報告あり)
食用タール系色素

発色が良く食品の見た目を鮮やかにする着色料で、石油由来なのが特徴です。
- 由来:石油由来の合成色素
- 主な用途: お菓子、漬物、かまぼこ
- 性状:赤、青、黄などカラフルな色
銅クロロフィル、銅クロロフィリンナトリウム
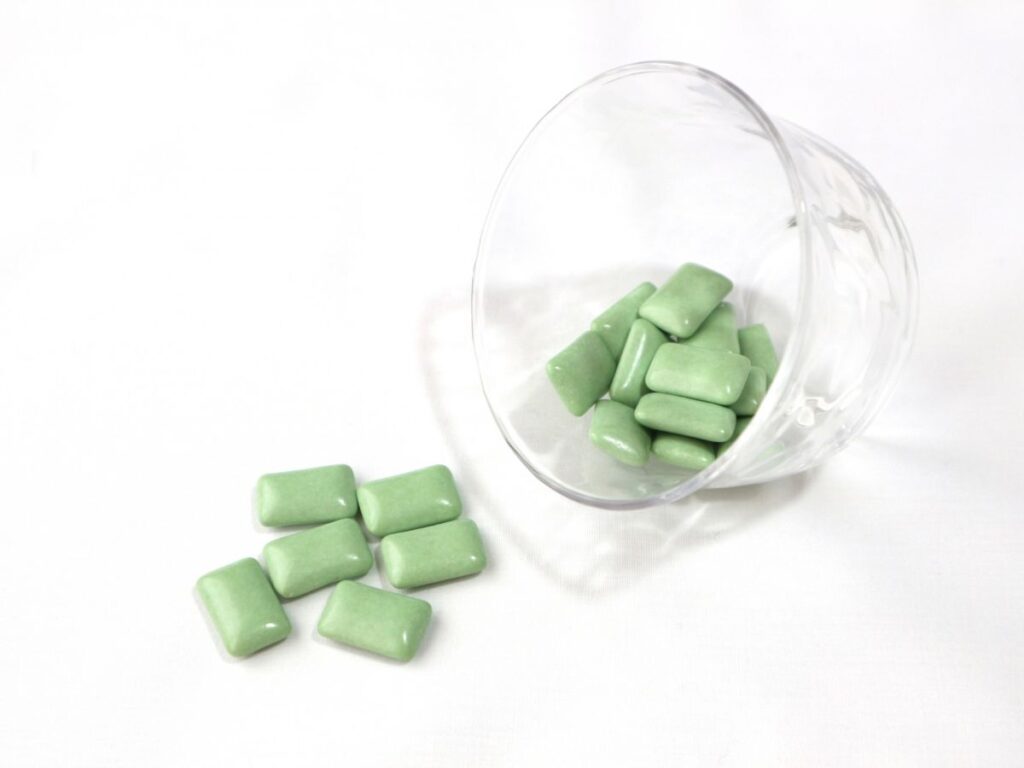
クロロフィル(葉緑素)を加工して作られる緑色の着色料です。
- 由来:葉緑素(クロロフィル)
- 主な用途:ガム、生菓子、チョコレート
- 性状:青黒~緑黒色
ベニコウジ色素

ベニコウジ菌が作り出す赤色の色素で、発酵食品由来です。
- 由来:ベニコウジカビ
- 主な用途:かまぼこ、ちくわ、調味料
- 性状: 暗赤色
ベニバナ赤色素・黄色素

ベニバナの花から抽出される色素で、古くから使われている着色料です。
- 由来:ベニバナ(紅花)
- 主な用途:漬物、清涼飲料水、菓子、麺類
- 性状:暗赤~暗紫色(赤)、黄~暗褐色
食品添加物の着色料が含まれる食品例
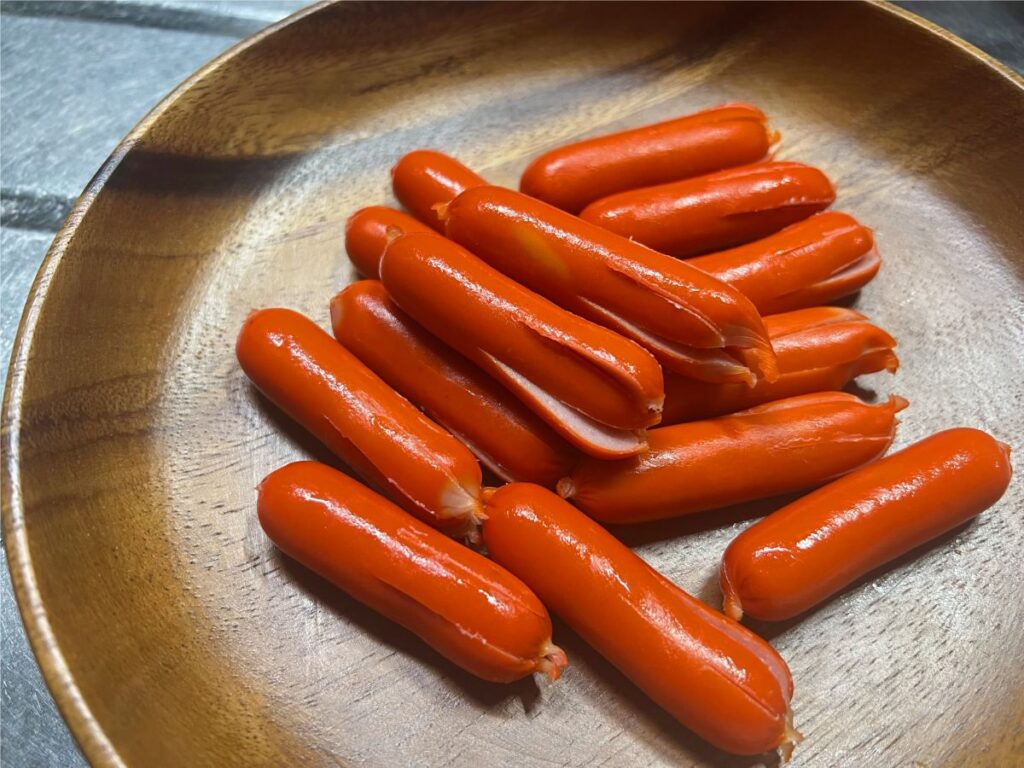
食品添加物の着色料は、以下のような食品に含まれています。
- スナック菓子
- ジュース・炭酸飲料
- 加工肉
- 漬物
- アイスクリーム
着色料は食品に多く使われていますが、選び方次第でリスクを減らせます。
自然由来の着色料が使用された商品を選んだり、着色料不使用の食品を選び、賢く選んで、健康的な食生活を送りましょう。
食品添加物の着色料に関するよくある質問

食品添加物の着色料とは?

着色料赤102は危険ですか?
EUでは一部使用制限があり、子ども向け食品に警告表示を義務付けています。
ただ、日本では許可されているため、食品の成分表示を確認し、「赤色102号」の記載があるものは控えめにするなどの対応がおすすめです。

食品に着色料を使う目的は?
着色料が使われる主な目的は以下の通りです。
食品の見た目を良くする:視覚的に美味しそうに見せるために、色鮮やかな食品が作られる
原材料の変色を防ぐ:保存中に変色してしまう食品の色を補うために使用される

着色料が多い食べ物は?
着色料は、以下のような食品に多く含まれています。

| 食品カテゴリ | 代表的な食品例 | 主な着色料 |
| お菓子・スナック | グミ、ゼリー、ラムネ、アイス | 赤色102号、黄色4号、青色1号 |
| 清涼飲料水・炭酸飲料 | カラメル色素、黄色5号 | |
| 加工食品 | かまぼこ、カニカマ、ハム、ソーセージ | コチニール色素、カラメル色素 |
| 漬物類 | たくあん、福神漬け | ウコン色素、赤色102号 |
食品添加物の着色料の知識を身につけて、より良い食生活を送ろう!

特定の着色料にはリスクも考えられますが、すべての食品添加物の着色料が危険なわけではありません。
食品添加物の着色料についての知識を身につければ、より健康的な食生活を送れるようになります。
着色料を完全に避けるのは難しいですが、「何を選ぶべきか」を知っているだけで、より安全で健康的な選択ができるようになりますよ。
近年では消費者の健康意識の高まりにより、「食品添加物不使用」「着色料不使用」の食品が増えています。
商品を選ぶときは原材料欄をしっかりチェックする習慣をつけましょう!
アイチョイスでは、主に愛知県・岐阜県・三重県・静岡県エリアでオーガニック食材や食品添加物に頼らない食品をお届けしております。
ぜひお得なお試しボックスをご検討ください。
送料無料で初回の方に限り3,400円相当が1,980円でお試しできます。







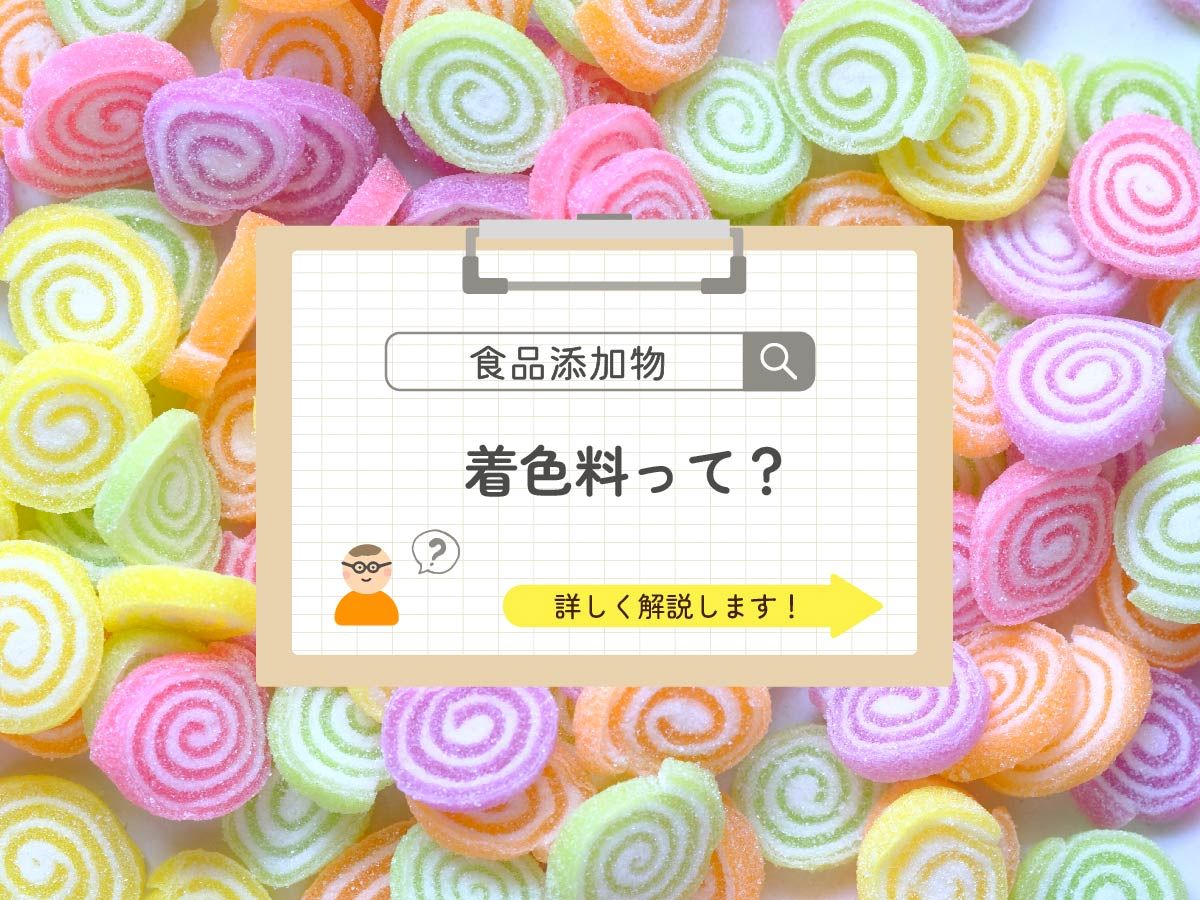




着色料とは、食品の色を調整するために使用される食品添加物の一種です。
食品の色調を改善するために使用。
植物・昆虫・微生物など自然由来の色素を使用した天然系着色料と、化学的に合成された色素で発色が良い化学合成系着色料の2種類があります。